形見分けで起こる相続トラブルとは?対処法や注意点・大切なマナーを解説

監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
![]()
監修者ベストロイヤーズ法律事務所
弁護士 大隅愛友
使途不明金や不動産の評価等の専門的な遺産調査や、交渉・裁判に力を入れて取り組んでいます。
相続の法律・裁判情報について、最高品質の情報発信を行っています。
ご相談をご希望の方は無料相談をお気軽にご利用ください。
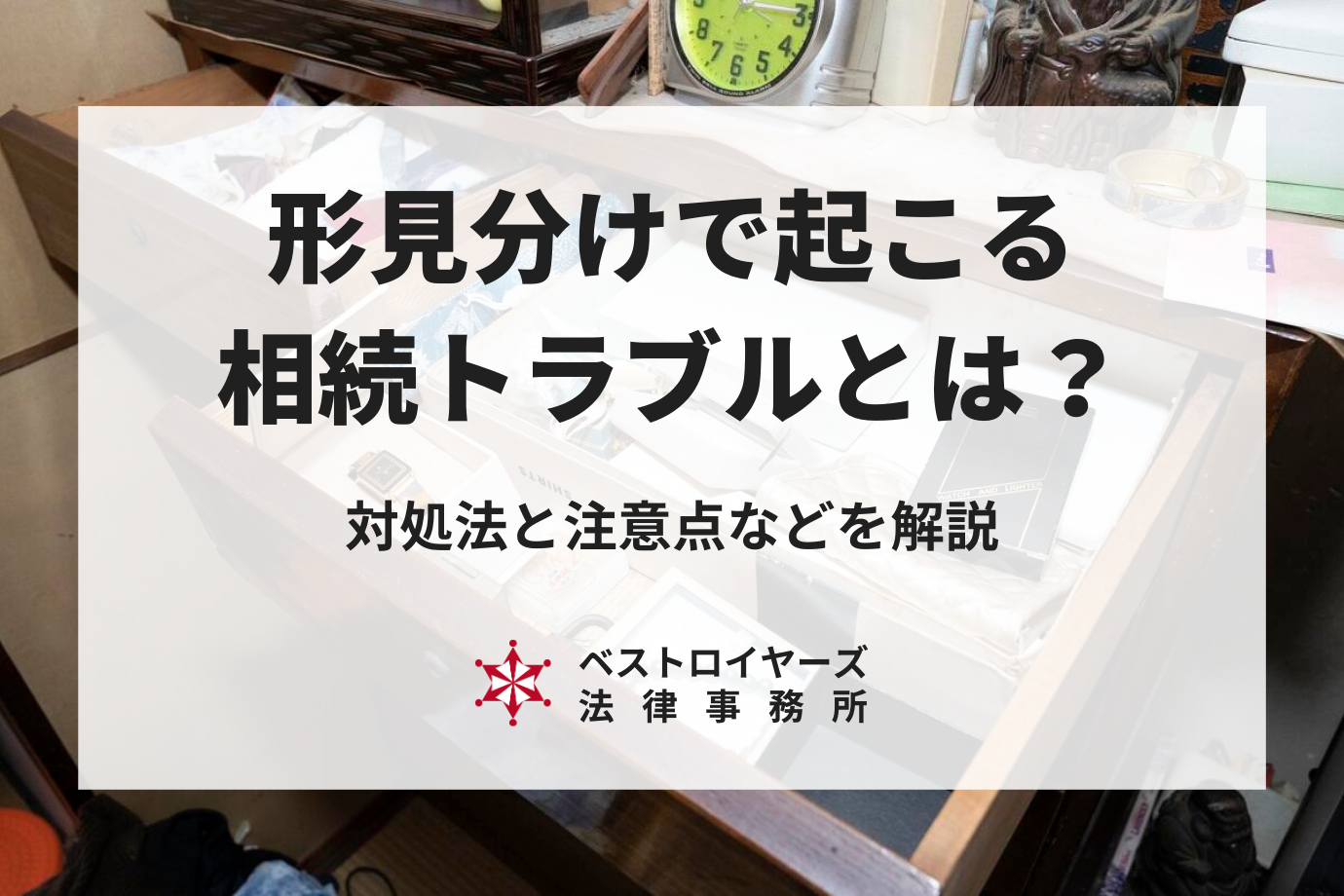
人が亡くなったときに残る遺品のなかには、故人との思い出がつまった大切な品もあるでしょう。
遺品は「形見分け」として、親族同士で話し合いながら分けあうことになります。
しかし、やり方を間違えてしまった結果、どれだけ仲の良い親族間にも亀裂が入ってしまう相続トラブルは珍しくありません。
相続トラブルが起きないよう事前に対策をしておけるとよいですが、準備ができなかった遺品整理をするというのであれば、正しい進め方をおさえておくと安心です。
この記事では、形見分けをすることで起こりうるトラブル例や、問題が起きた場合の対処法、形見分けをする際の注意点をご紹介します。
現在、形見分けの相談受付はしておりません
ただいま鋭意準備中です。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
1 形見分けとは?故人との思い出を大切にするのが目的

「形見分け」とは、亡くなったかたの遺品を整理して分け合うことです。
形見分けじたいは義務ではないので、受け取る人たちのマナーが重視されます。
親族や生前親しくしていた人たちは遺品を受け取ることで、故人を近くに感じることができるもの。人を失ってぽっかり開いた穴をうめ、故人との思い出を大切にあたためることを目的として、形見分けをおこないます。
できることなら平穏に分け合ってお話を済ませたいところですが、いざ遺品整理をしてみると話がまとまらず、トラブルになってしまうことは珍しくありません。
【関連記事】遺品整理業者とのトラブルを避けよう|予防策から揉めた場合の対処法まで解説
1-1 形見分けと相続の違いは?
形見分けの特徴は、分けるものの対象が「財産としてはほとんど価値のないもの」である点です。
「財産として価値がある」と判断されるものは、相続対象として相続人間で分割(遺産分割)する必要があります。
【関連記事】遺産分割調停に必要な費用とは?相場・手続き方法を解説
相続をする場合には、法にしたがいながら正しく手続きをする必要があり、場合によっては相続税も支払わなくてはいけません。
また、相続にあたり法定相続人のすべてによる同意が必要になるケースもあるため、遺品には勝手に手をつけず、相続手続きに入りましょう。
1-2 形見分けをするのはいつ?
形見分けをしなくてはいけないタイミングは、特に決まっていません。
とはいえ一般的には、亡くなってから49日の法要が終わった「忌明け(きあけ)」がよいとされています。
四十九日法要のタイミングで親族も集まりやすいため、故人をしのぶ意味も込めて、形見を手に取りながら話し合いをしてみてはいかがでしょうか。
2 形見分けで起こりやすいトラブルとは?

形見分けで起こりうるトラブルはおもに、「誰が何を譲り受けるか」です。
トラブルに発展しやすい原因は、たとえば下記があげられます。
①口約束をした
②あやまって品を捨てた
③知らない第三者からの申し出がある
それぞれについて、事例をご紹介していきます。
2-1 口約束をした
口約束をしただけ、というケースは後々、親族間でトラブルになりやすいです。
たとえ約束をした理由や経緯を説明したとしても、証拠がなければ嘘である可能性を疑われやすく、納得してもらいにくくなります。
また、たとえ信憑性があったとしても、平等性に欠けることから同意が得られないことも。
とくに下記のような物品は、トラブルに発展しやすいです。
・ジュエリー
・絵
・書物
・着物
・コレクション
・食器
高価なものほど「受け取った後に売って儲けようとしているのでは?」と怪しまれてしまいやすくなります。
約束をするときには遺言書やエンディングノートに書き記しておくこと、あるいは数人いる親族の前で約束をすることが大切です。
【関連記事】誰でもできる終活ノートの作り方!手順や留意点を弁護士が解説
【関連記事】遺言書の書き方~自筆で書く遺言のポイントと注意点を弁護士が解説
2-2 あやまって品を捨てた
誰かにとってはゴミのように見えるものにも、当事者にとってはとても大切な思い出がつまった品である可能性があります。
遺品整理のために勝手に処分をしたり、物を移動させてしまうことにより、あやまって処分・紛失してしまうことはトラブルに発展しやすいです。
とはいえ、一度捨ててしまったものは、もう手元には戻ってきません。その後の親族間のトラブルにならないよう、遺品に手をつける前にしっかりと形見分けの話し合いをしておきましょう。
2-3 知らない第三者からの申し出がある
遺品整理をしていると、第三者から「形見分けとして譲ってもらいたいものがある」などと連絡が入る場合があります。
親族がよく知らない相手でも、実は故人が生前に親しくしており、形見を受け取る約束をしていたなどというケースがありえなくはありません。
たとえば隠し子や愛人がいた場合などは、大きなトラブルに発展しやすいです。もし血縁などの深い関係性があると主張するのであれば、戸籍を調べてみてください。
【関連記事】代襲相続とは?相続できる範囲やできる、できない、トラブルまで解説
【関連記事】特別縁故者となる要件は?財産分与までの流れを弁護士が解説
第三者のことを知らないからと言って門前払いするのではなく、しっかりと話を聞いてみましょう。
3 形見分けでトラブルが発生した場合の対処法とは?

形見分けをしていてトラブルが発生したときには、親族どうしで言い合いになってしまうかもしれません。
でも、一度冷静になって、落ち着いて対処しなくては話は進みません。
具体的には、下記のような方法で対処してみてください。
①話し合いをかさねる
②高価なものは相続対象にする
③弁護士に相談する
それぞれのコツについて、詳しく解説します。
3-1 話し合いをかさねる
形見分けなど親族間で話し合わなくてはいけないことが複雑化すると、解決を後回しにしたくなるでしょう。
でも、ときが経ったとしても状況は変わりません。
まずはトラブルの原因をしっかりと明確にして、どうすれば和解できるのか解決案を出し合いましょう。
感情的に話し合ってしまうと関係性がさらに悪化し、形見分けをきっかけに親族が不仲になってしまうこともあります。
かならず冷静になって、広い視野を持ちながら話し合いましょう。
3-2 高価なものは相続対象にする
形見分けで不穏な空気が流れやすいパターンは「これは生前に私が譲り受けることを約束した」と、比較的高そうなものの引き取りを申し出る人がいた場合です。
たとえばリビングにある大きな絵画や、数多く揃っている食器のコレクションなどの高価そうなものは「本当は売るつもりでは?」とあやしまれる傾向があります。
みんなにとって思い出があり、本当に形見として譲り受けたい人が複数人いる場合には、相続財産と同様に金銭で精算することも視野に入れてみてはいかがでしょうか。
もし売った場合にいくらになるのかなども調べたうえで、みんなが納得するように分け合ってみましょう。
なお、財産価値が高いものについては相続税の対象となる可能性があるので、自分たちだけで判断した結果「相続税を払わなくてはいけなくなった!」となることもあります。
また相続人ではない人が高価なものを受け取るときにも、贈与税の対象となる可能性があるので油断はできません。
トラブルになっている原因が高価なものであるならば、相続対象にする必要の有無を見直してみるとよいです。
3-3 弁護士に相談する
どうしても親族間だけで話し合いがまとまらない場合には、第三者としてプロである弁護士を間に入れるの手段の一つです。
問題を法律とてらしあわせながら、平等な立場で判断するからこそ、みんなの納得できる結果へと導ける存在となるでしょう。
ただし、弁護士を雇うためには費用が必要です。
費用を誰がどう負担するのかについても話し合う必要がありますが、どうしても話がまとまらずストレスのたまる時間を過ごし続けるよりはよいのかもしれません。
4 形見分けでトラブルを避けるための注意点とは?

形見分けでは、親族間のトラブルがつきものです。
そこで、必要以上の問題を抱えストレスにしないためにも、下記のような注意点をおさえておくことをおすすめします。
①遺言書やエンディングノートの有無を確認する
②無理に渡そうとしない
③故人より目上の人に渡さない
それぞれについて、詳しくお伝えします。
4-1 遺言書やエンディングノートの有無を確認する
もし遺言書やエンディングノートが見つかった場合には、あくまで故人の意思を尊重して形見分けをおこないましょう。
形見分けは相続と違い、法律で厳しい決まり事が定められているわけではありません。
だからこそ、本人が残した意思はそのまま、親族が受け取ることができます。
遺言書やエンディングノートを残しているということは、親族に争ってほしくないという想いの表れでもあるでしょう。
記載されている内容を尊重し、形見分けをおこなってくださいね。
なお、遺言書が見つかった場合には開封をせず、家庭裁判所へ検認に出さなくてはいけないことが法律で決まっています。
あやまって自分たちで開封しないよう注意しましょう。
【関連記事】自筆の遺言は開封前に検認が必要!必要書類や注意点・手続きの流れを手順で解説
【関連記事】遺言書を兼任しないとどうなる?リスクや手続きの方法を弁護士が解説!
4-2 無理に渡そうとしない
もし形見分けが不要だという人がいたら、無理に渡そうとする必要はありません。
たとえば、一見すると親しそうだった人に形見分けをしようしたところ、「思い入れのある品を私が受け取るわけにはいかない」などと断られる場合などは、大いに考えられます。
正直なところ不要なものを受け取っても、こっそり処分しなくてはいけなくなるのはしのびないと感じてしまうものです。
受け取る側の意思も尊重して、遠慮をしたいという人の声は受け入れましょう。
また、相続放棄をした人については、形見分けをするのもよくありません。形見分けが理由で相続放棄ができなくなってしまうこともあるので、注意してください。
【関連記事】身内が孤独死してしまったら?相続放棄をすべきケースや注意点
4-3 故人より目上の人に渡さない
故人よりも目上の人に形見分けをするのは、失礼にあたると言われています。形見分けをするものは基本的に、資産価値として経年劣化したと考えられるはずです。
本人が形見分けを希望している場合をのぞき、目上の人に渡すのはマナー違反であり、トラブルの原因にもなりえるようです。なお、形見分けはプレゼントではないので、親族以外に渡す場合にも過剰にきれいに包む必要はありません。
とはいえマナーとして、なるべくきれいな状態にして半紙に包むなど、気持ちよく受け渡しができるとよいですね。
5 まとめ:形見分けでトラブルが起きたら冷静に判断しよう

形見分けではトラブルが起こりやすいことを理解して、生前に集まり話し合いをしながら分けられるのが理想的です。
しかし、終活をすることに抵抗がある場合や、急な出来事だった場合には、形見分けに関する話し合いがうまく進まないことが珍しくはありません。
遺言書やエンディングノートがない場合には、たとえ口約束をしていたとしても、思っていた通りに形見を分けてもらえない可能性があります。
また遺品に財産としての価値がある場合には、相続手続きが必要になるかもしれません。
形見分けをするときには広い視野を持ち、どのような対応が正しいのか判断しましょう。
現在、形見分けの相談受付はしておりません
ただいま鋭意準備中です。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
![]()
使途不明金や不動産の評価等の専門的な遺産調査や、交渉・裁判に力を入れて取り組んでいます。
相続の法律・裁判情報について、最高品質の情報発信を行っています。
ご相談をご希望の方は無料相談をお気軽にご利用ください。

 ご予約
ご予約